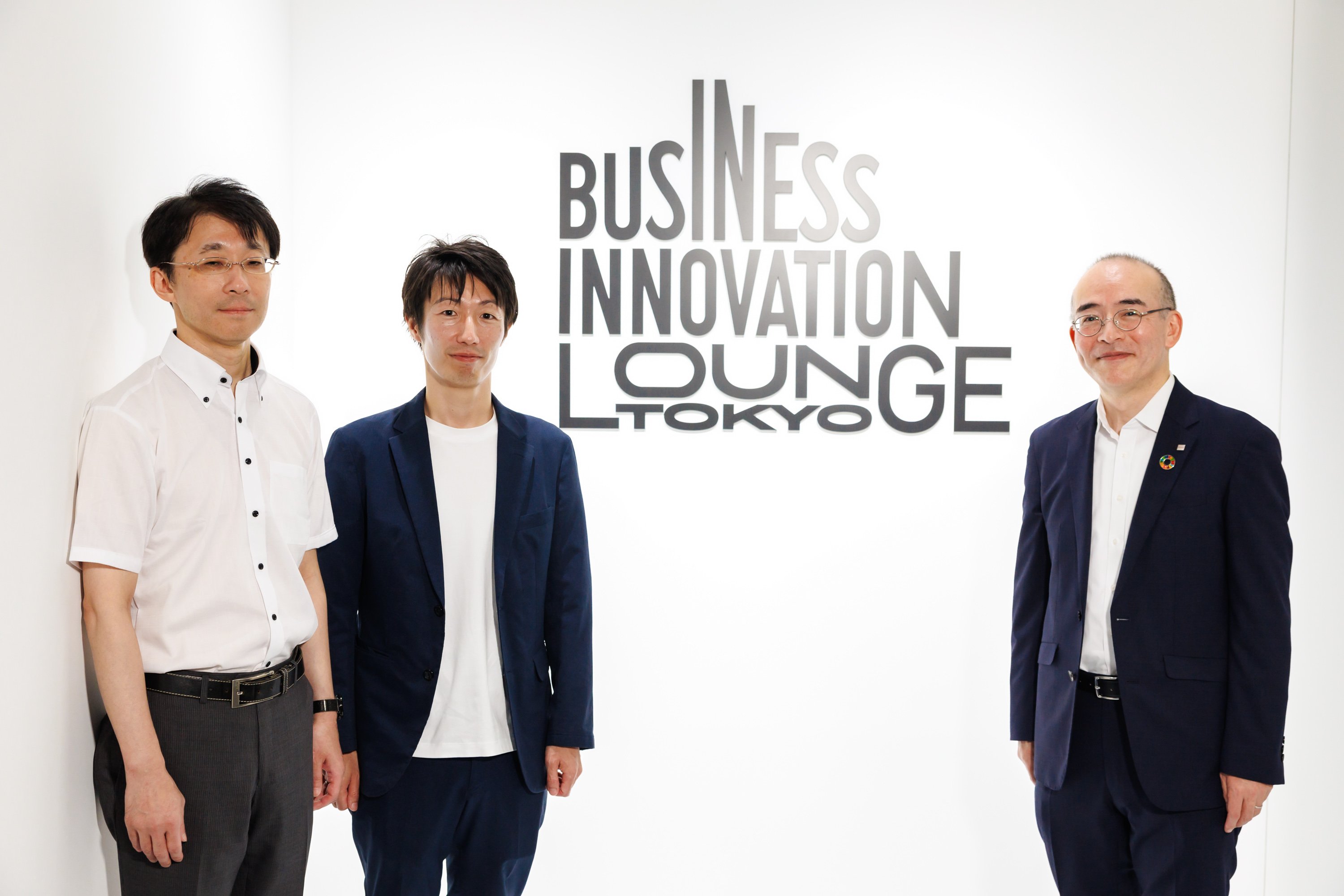
「RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO(以下RICOH BIL TOKYO)」は、企業間の垣根を越えたコミュニティを形成する場として、リコーが提供するスペースだ。クライアントはここでの対話と体験を通して未来の構想を練り、リコーが使命として掲げる「“はたらく”に歓びを」を共に実現すべく、パートナーとして伴走していく。施設の全容や、協働で進んでいる最先端技術を応用した事業を紹介しよう。
オープンイノベーションから生まれたアイデアを具現化する場所
品川にある「RICOH BIL TOKYO」がオープンしたのは2024年2月。田町にあった拠点を移転・拡大したものである。最新のAI技術を活用しながらクライアントとの共創活動を強化する取り組みは、以前から存在した。RICOH BIL TOKYOが迎えるのは、基本的に企業の経営者層だ。自社の課題を把握し、なおかつ決定権を持っていて行動に移すまでが早いからである。RICOH BIL TOKYOビジネスデザイナーの千代直貴さんはこう説明する。
「事前に打ち合わせをし、課題に対してこちらからご提案できるものを用意しておきます。当日は事前情報を元に構成したデモエリアで我々の技術を体験していただき、その後、顕在化している問題や取り組むべき課題領域を共有し、解決策を一緒に構築していきます」

ビジネスデザイナー:千代 直貴氏
こうした「共創」を、リコーは登山のイメージで捉えている。ゴールのイメージに共感する人々とパーティーを組み、未踏の山頂をともに目指すのだ。RICOH BIL TOKYOの空間デザインも、この登山のイメージを体現している。まずは巨大なLEDビジョンの映像を前にしたラウンジで10分ほど対話をし、リコーの担当者とプログラムのゴール(山頂)を共有する。デモ体験スペースに通じる暗く狭い通路は、洞窟を模している。登山の第一歩を感じさせ、期待が高まる空間演出だ。この通路を抜けるとそこにあるのが、四角いスペース。「生産性の追求から創造性の発揮へ」という今日のオフィスに求められる在り方を、360度全面ビジョンで表現する次世代会議空間で、創造力が刺激される。デモ体験の前に、マインドがいったんリセットされる感覚だ。
デモエリアには、開発中の先進的なプロダクトやデジタルサービスが展示されている。クライアントの関心領域に最適化されたツアーで、新しいアイデアや課題解決へのヒントが生まれるわけだ。ひと通りのデモ体験が済んだら、もうひとつのラウンジに戻り、落ち着いた空間の中で課題をさらに掘り下げていく。スタートから約2時間をかけたセッションで、具体的なアクションにつながるレベルまで突き詰めるというから、かなり濃密で有効な時間だ。実際にプロジェクトが走り出したら、ワークショップのための部屋やラボ、チームの拠点となる専有スペースも提供され、思う存分試行錯誤ができる。
「さまざまな領域の専門家に加え、ビジネスデザイナー、デザインシンカー、エンジニア、DXコーディネーターなどがクライアントの同伴者としてプロジェクトを運営し、仮説検証をリードします」
リニューアル前の時点(2018年〜23年)でRICOH BILTOKYOの総来場社数は860社に上る。最先端の技術を用いた課題解決プロジェクトが、これまでにいくつも誕生しているのだ。
信頼性の高い回答が特徴のデジタルバディおよびデジタルヒューマン

RICOH BIL TOKYOのラウンジで対話をする際に、サポート役として登場するAIキャラクターがいる。デジタルヒューマン、だ。
「デジタルヒューマンは、音声対話で業種・業務支援を行うことを目的に開発されました。例えば当社のデジタルヒューマンは、商談を手伝ってくれるAIです」と言うのは、デジタル戦略部の本林正裕氏である。
LEDビジョンに映し出されたデジタルヒューマンをはさむようにクライアントとリコー担当者が座る。デジタルヒューマンの自然な会話力は同社の大規模言語モデルによる学習機能の成果であり、「3人」の会話は円滑に進んでいく。議事録の作成も自動で任せられるのが便利だRICOH BIL TOKYO に導入された2月以降、デジタルヒューマンに着目する企業が増えているという。
「RICOH BILTOKYOのデジタルヒューマンは当社のデータを学習しており、会話の中から適切と思われるサービスを見つけて提案したり、その効果を具体的に解説したりして営業メンバーをサポートします。当社の音声認識技術、RAGを活用したAIモデルにより、回答精度は非常に高いと言えるでしょう。デジタルヒューマンは検証段階ですが、まずは介護、アミューズメント、営業、教育という領域での実証実験を考えています。『オフィス空間づくり』に強みを持つITOKIさんも、当社のパートナーとして開発に携わっていただいているところです」

室長:本林 正裕氏
デジタルヒューマンは、人と違って疲弊しない。24時間365日稼働できる。時間と場所にとらわれないというメリットは、店頭での接客はもちろん、教育領域での効果が期待される。デバイスさえあればどこにいても高い教育を受けることが可能になるため、教育インフラの偏在という課題を解決できるからだ。将来的にはあらゆる業界・業種への適用が考えられ、反響の大きさも当然だろう。
精度の高い言語処理能力を生かしたサービスとしては、「RICOHデジタルバディ」も2024年の6月にリリースされている。こちらはRAG(検索拡張生成)技術によるチャットボットだが、大規模言語モデルが採用されているため、あやふやな内容の問いかけにも対応できる柔軟性が特徴だ。登録した自社データ(ドキュメント)から回答を生成するのだが、こうした企業のデータは、そのまま読み込むとハルシネーション(事実に基づかない回答)を起こすケースが多々ある。リコーでは防止の仕組みを採用し、回答の信頼性を上げている。参考リンクが回答と併せて表示されるため、根拠が明らかな点も評価が高く、自社専用かつ信頼性の高いAIとして多方面で重宝されるだろう。
イトーキとの共創でデジタル先生「ぐりん」が誕生
RICOH BIL TOKYOオープニングイベントでの出会いをきっかけに、教育分野でのAI活用を模索していたイトーキとデジタルヒューマン共創プロジェクトがスタートし、デジタル先生の「ぐりん」が誕生した。
「ぐりん」は、前述のデジタルヒューマンをベースとしたデジタル先生で、生徒の問いに寄り添う存在として、2024年9月に飛騨市の私塾「Edo New School」で中高生を対象とした探求学習プログラムで実証運用、また、2025年2月には飛騨市立古川中学校のデジタル校長先生として実証試験を実施した。先行実績から短期間の開発でRAGまで実装できたのも、共創の成果と言えるだろう。

デジタル先生 「ぐりん」
詳細:https://open-dx-lab.itoki.jp/articles/edtech/
RICOH BIL TOKYOの成果報告
2025年2月、RICOH BIL TOKYOの一周年イベントでの登壇で、イトーキはこのデジタル先生「ぐりん」を成果として報告した。
これまで取り組んできたイトーキのスマートキャンパスソリューション(学校の学ぶ環境、カリキュラムの高度化提案)の文脈に、デジタルヒューマン技術の可能性を融合させた、先進AI技術を用いた学ぶ環境のアップデートの試みだ。
生成AIを用いたエージェントをいち早く教育の現場に取り込み運用している様子に、会場からは驚きの声があがっていた。

株式会社イトーキ ソリューション事業開発本部 デジタル技術推進統括部 統括部長 大橋一広
RICOH BIL TOKYOを拠点にいくつものプロジェクトが進み、多くの企業が課題を解決してきた。「“はたらく“に歓びを」、リコーが掲げる理念はグループを越えて着実に広がっている。
プロフィール
押元 努(おしもと・つとむ)
リコージャパン株式会社
エンタープライズ事業本部 アライアンス・パートナー営業本部 ソリューション推進部
プロデュースグループ アシスタントマネージャー
千代 直貴(ちよ・なおき)
株式会社リコー
RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO ビジネスデザイナー
本林 正裕(もとばやし・まさひろ)
株式会社リコー
デジタル戦略部 デジタル技術開発センター 営業DX開発室 室長

