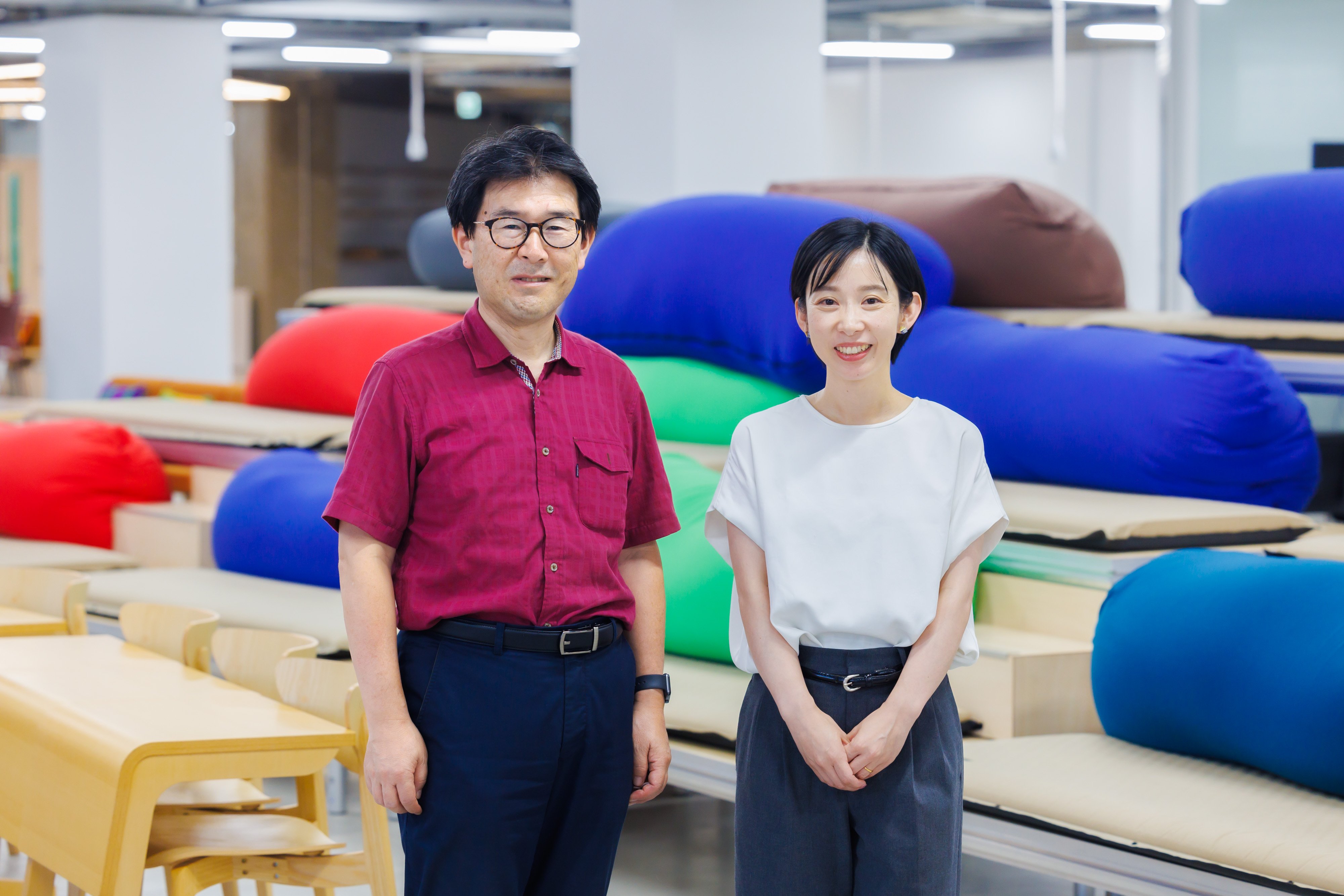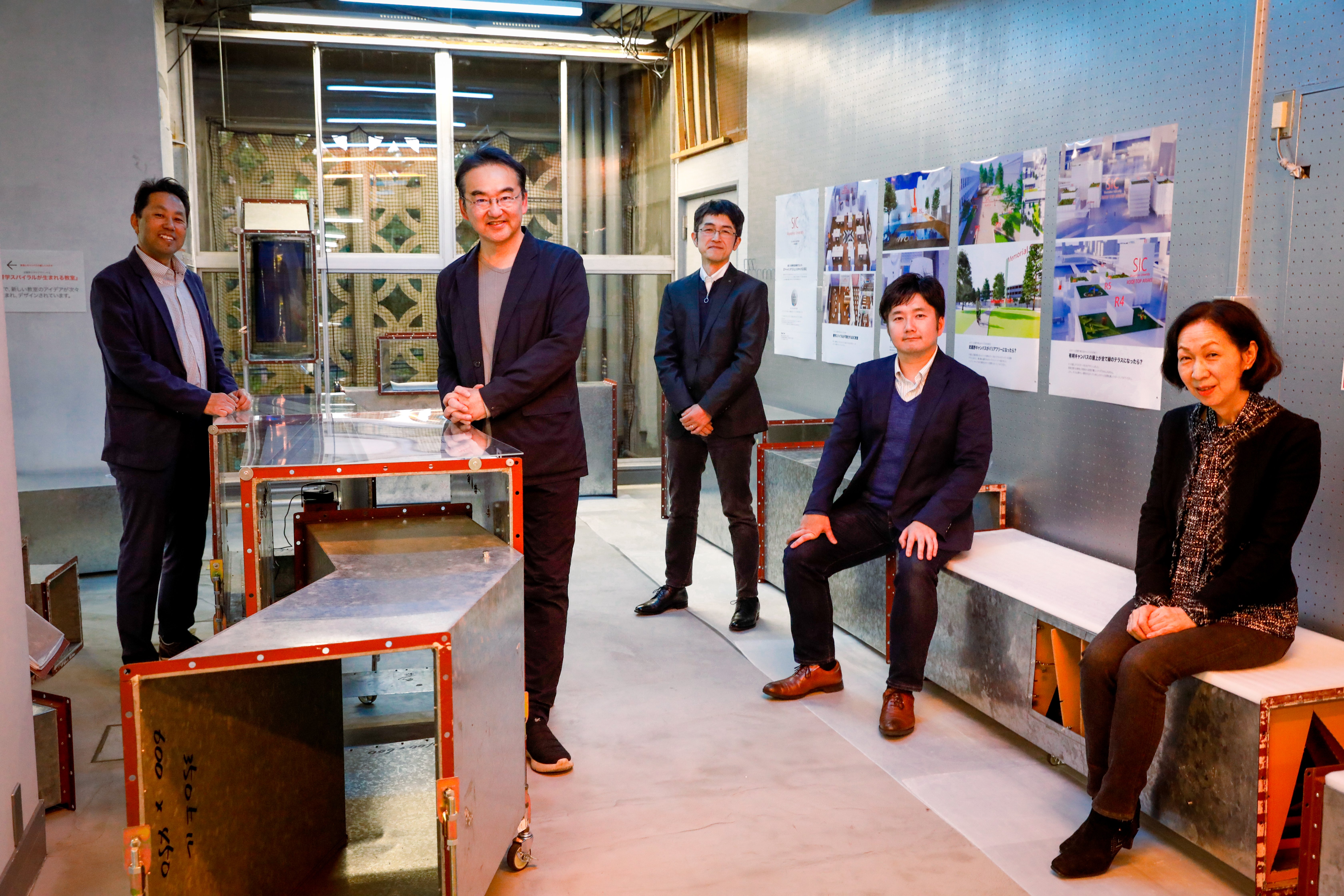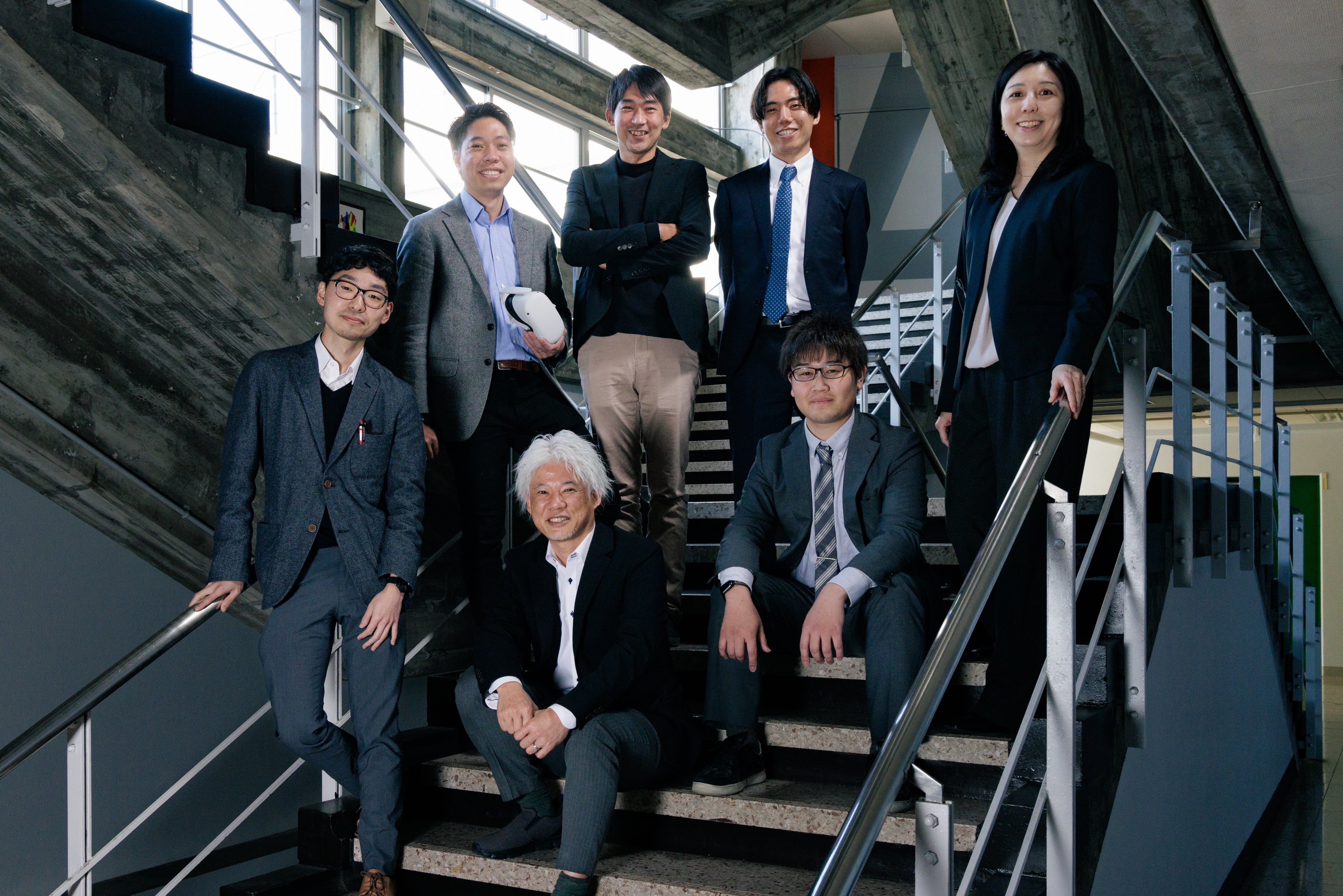2019年12月に文部科学省が開始した「GIGAスクール構想」のもと、児童・生徒への1人1台端末や通信環境の整備が進み、「教材のデジタル化」や「学習ログの蓄積」といった教育環境のデジタル化がますます加速している。
こうした環境変化が、授業カリキュラムや教育スタイルなど学びのあり方そのものに影響を及ぼしつつある今、学びの場においても変容/再定義が求められている。デジタル端末の文具的な活用は、学びのDXの入り口に過ぎない。生徒の探求心を育みつつ、多様性を発揮し自由に自己表現を行える環境の構築が、次のトランスフォーメーションの取り組みとして重要になるだろう。
イトーキは、静岡県の静岡聖光学院中学校・高等学校とともに、メタバース技術を活用した新しい教育スタイル、次世代の学びの場の研究を行っている。本稿では、研究プロジェクトのリーダーを務めるDX推進本部デジタル技術研究所の小澤照が、これまでの取り組みについて解説する。
静岡聖光学院には、ロボット制作や海洋生物の調査など、生徒が深く興味関心を持った分野に対して研究活動を行う「自然科学部」という部活があります。これまで、生徒たちによる研究成果の発表は文化祭などでのポスター展示や、教室に持ち込める範囲の実物による展示となっていました。私たちは、この研究発表の「場」に着目しました。もちろん、こうした従来型の発表方法でも十分生徒の皆さんの個性や気持ちを伝えられていたと思います。しかし、デジタル技術を活用することで、より表現の幅が広くなり、様々な物理的制約を気にすることなくもっと自由な発表が行える環境をつくれるのではないか、そう考えたのがプロジェクトの始まりでした。
今回は、デジタルを活用した研究発表の「場」として、メタバース技術にチャレンジしています。そこで、まずはメタバースがどんなものなのか生徒の皆さんに体験していただくために、イトーキの研究員と生徒の皆さんでメタバース空間に入り、リアルの教室でコミュニケーションを取るようにアバター同士での会話を行いました。

メタバース空間では、リアルの教室と同じように室内を動き回ったり、話したい人に近づいていき会話することができます。一方、リアルの教室ではポスターの展示や模型を置くなど、スペースや機材の制約から画一的な展示方法になりがちなところを、メタバース空間では動画を壁面に張り付けたり教室に持ち込めないような大きなものを持ち込んだり、物理法則を無視して物体を宙に浮かせたりなど、自由に表現することができます。リアル空間では不可能なことが、メタバース空間では可能になるわけです。
生徒の皆さんには、メタバース空間がいかに自由な表現が行えるかを知っていただき、表現の手段における固定概念をリセットしたのち、研究活動に打ち込んでもらいました。


現在は、2022年10月1日(土)・2日(日)に開催される文化祭(聖光祭)での研究発表に向けて、研究成果のまとめ、発表を行うメタバース空間作りに取り組んでいます。研究成果のまとめはもちろんのこと、発表を行う空間作りも生徒自身の力で行っています。
これまでにない、斬新かつ先進的な文化祭での発表に、イトーキのプロジェクトメンバーも、とてもワクワク、期待しています。文化祭の模様は、レポートの第2弾でお届けします。どうぞご期待ください。

静岡聖光学院高等学校の生徒たち×ITOKIのプロジェクトの様子は、こちらのサイトでもご覧いただけます。
聖光見聞録~学校ブログ~ ITOKIさんとのVRレッスン【聖光見聞録1161】
https://kenbunroku.s-seiko.ed.jp/1161-
聖光見聞録~学校ブログ~ VRプロジェクトレッスン第2弾【聖光見聞録1164】
https://kenbunroku.s-seiko.ed.jp/1164-
静岡聖光学院中学校・高等学校
http://www.s-seiko.ed.jp/