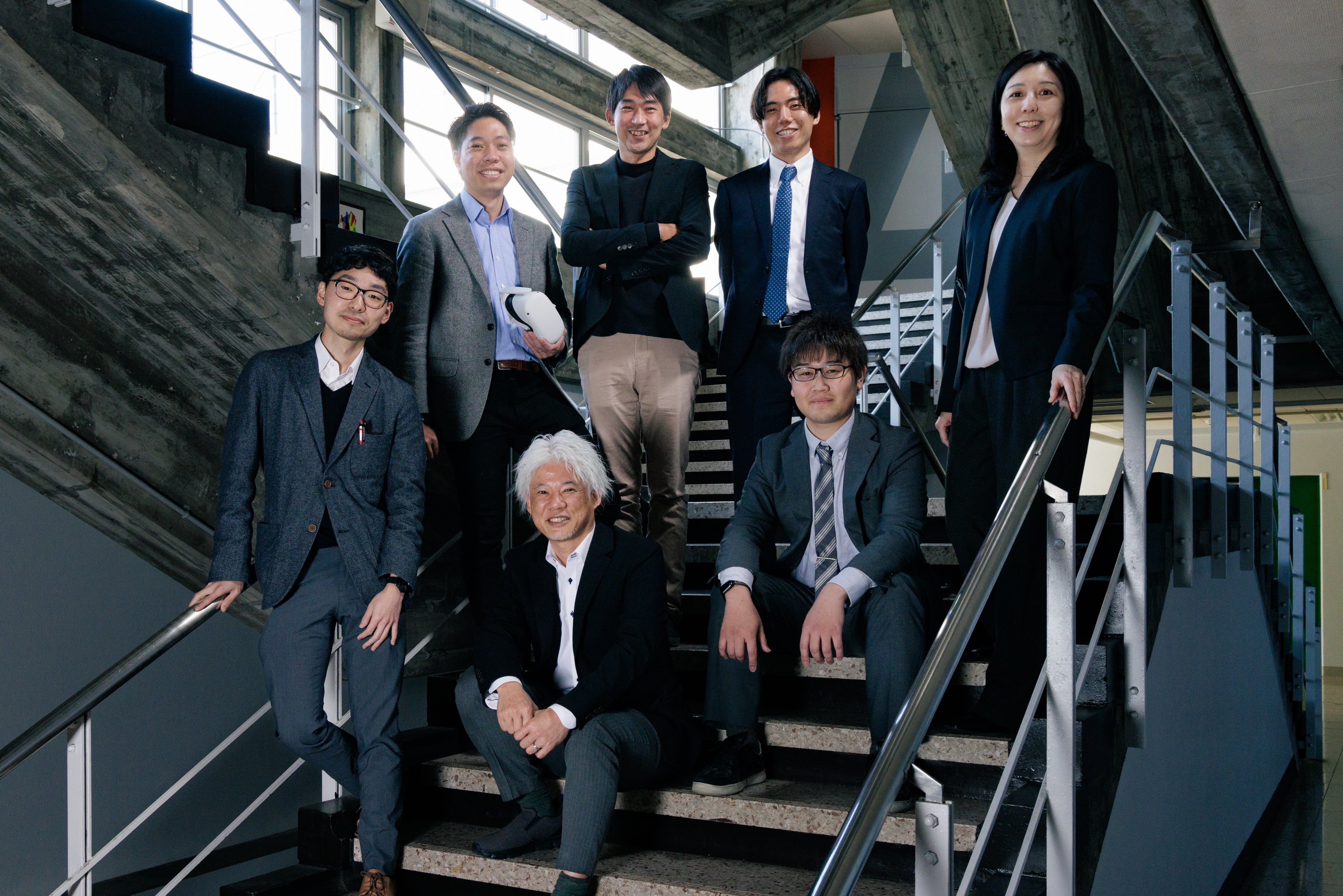
イトーキと静岡聖光学院は、令和4年度文部科学省『次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業 』の採択を受け、生徒らがメタバース空間を活用して個性を生かした表現活動を行う「研究発表会」と海外と接続し交流を行う「国際交流会」の実証研究を推進した。メタバース空間は学びの場としてどのような意義をもたらすのか、さらなる活用可能性の道程はどこへ向かっていくのか―。推進メンバーおよび本事業の事務局担当者らが集い、座談会形式での成果レビューについてレポートする。
<出席者>
◇静岡聖光学院中学校・高等学校
事務係長 武田 光一郎 氏
教諭(英語)英語科主任 国際部 ICT推進委員長 中村 光揮 氏
教諭(数学)数学科教諭 秋本 裕太 氏
◇EY新日本有限責任監査法人
CCaSS事業部 シニアマネージャー 池田 宇太子 氏
CCaSS事業部 岡本 祥平 氏
◇株式会社イトーキ
DX推進本部 デジタルソリューション企画統括部 デジタル技術推進部
宮前 太一
小澤 照
<聞き手・文>
国際大学GLOCOM
主幹研究員/研究プロデューサー 小林奈穂
キーワードは「どこでもドア」。メタバースは、時間や空間を越えた学びを実現する。
―メタバースの学習活用、とても先駆的で面白いテーマです。このテーマにたどり着いた背景や、プロジェクト始動のきっかけを教えてください。
中村:2020年以降、新型コロナウイルスへの対応策として各教室にオンライン授業用にカメラやパソコンなどの機材を導入し、授業を遠隔で届けられるようになりました。オンラインはリアルでの授業を代替できる。しかし、代替としてのテクノロジー活用が本当に生徒たちにとっての必要な学びに繋がるのか、という疑問に行き当たったのです。「リアルに会って学ぶこととオンラインで学ぶことの違いは何か」、「次に必要な学びにテクノロジーがどう寄与するか」について、本腰をいれて真面目に考えるようになったのです。
武田:コロナ禍になって教職員しか学校にいない状況のなか、若手の先生方と研修会を開いて「これからどういう学校を目指すのか、どういう学校にしたいのか」を考えました。将来像を探っていくうちに、「どこでもドア」というキーワードがでてきました。
今回実証研究で利用した教室は、BIGIRION-Garage(ビギリオン・ガラージ[i])といってSTEAM教育のためにつくった空間ですが、真の目的は生徒たちが普通の教室とは違う「異空間」で学びに向かうスイッチを切り替え、学びへの意識改革をもたらすことにあります。
この「異空間」をさらに発展させて、時間と空間という制限を全て取り払うとしたら、と考えた結果が、メタバースだったわけです。さっそく教員たちと廉価版のVRゴーグルを購入する予算を通して、まずは「半分遊び」でやってみよう、ということになりました。
[i] BIGIRION-Garage(ビギリオン・ガラージ)とは、美術のBI、技術のGI、理科のRI、音楽のONを繋げた造語。ハイスペックのPCや3Dプリンター、隣室には工房を備えており、生徒たちが、やりたいことを好きなだけやれる創作空間となっている。
静岡聖光学院中学校・高等学校ウェブサイト|学校案内|施設・設備
http://www.s-seiko.ed.jp/school-guide/facilities/

―先生方が意識的に「遊び」として始めたプロジェクトなのですね。
武田:真面目すぎると続かないと思います。特に在宅のオンライン環境では、あまり堅すぎてもたぶん嫌になってしまうと思います。少しの遊び心を持って、ゲーム性を取り入れたほうがなじみやすいだろうと考えました。でも、実際やってみると、よく分からないこともありました。そんなとき、イトーキの小澤さんたちと出会いがあり、加速度的にプロジェクトへと進化したのです。
小澤:何でもトライをしてみようという静岡聖光学院さんと、新しい技術をいかに学びの場に適用できるかを検証したいという我々イトーキのモチベーションが重なりました。プロジェクトの狙いは、メタバースによって生徒のコミュニケーションをより充実したものにし、より自由な表現力を育てていくことにありました。具体的には、メタバース空間上に海外の同世代の子どもたちと集い国際交流を行う実践と、もうひとつは部活動の成果発表会をメタバース上で開催するという2つに取り組みました。

― 部活動の成果発表会とは、どのような内容でしょうか?
秋本:私が顧問をつとめる自然科学部の生徒たちは、毎年文化祭で、それぞれの研究テーマの発表をします。これまでは、ポスター発表が中心でしたが、二次元のメディアで表現できることには限界があります。
例えば、生徒たちが研究したいことは、ドローンのプロペラの細かい部分や形、ミニ四駆の細かい後ろに付いているリアウィングの形だったりします。形の違いによって、速さにどう影響するのか、ということは二次元空間では表現しづらい。そこで、メタバース空間を自分のこだわりを表現する方法のひとつとして捉えるのが面白いのではないか、と考えたのです。そこで、文化祭での研究発表を、メタバース上で行うことになりました。
―この取り組みは、文部科学省による事業に採択されたそうですね。文部科学省の狙いはどこにあるのでしょうか。
岡本:令和4年度の「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業」では、10団体の事業が採択されました。先端技術の教育利用には、メタバースのほかセンシング、個人情報、学習データの利活用など、様々なものがあります。こうした技術活用の適用先と、展開先を広げることが目的です。
私個人としても、メタバース技術は、不登校の支援、貧困、いじめの防止など学びにおけるリスクへの対応と、探究学習などの創造活動への活用可能性に期待を寄せています。

メタバースはリアルの代替ではない。生徒が自らデザインすることで、創造性の発揮とコミュニケーション機会を拡張する第3の空間だ。
―自己表現の手法や創造活動の対象としてメタバースを活用するとき、他のメディアやツールとどのような違いや効用があるのでしょうか。
宮前:メタバースでは空想の世界を作ることができます。しかし、今回は教室の空間デザインを全くそのまま、研究発表の場としてメタバース上に再現しました。人間の認知は常に対比をしますから、リアルと同じ空間が仮想上にも空間がある、という状況をあえてつくり、それが子どもの認知に及ぼす影響を検証しようと考えたのです。まだ詳細にリアルとの違いを立証するには時間がかかりますが、生徒たちの反応から、明らかに空間の見え方で振る舞いが変わっていることが見てとれました。メタバースはリアルを代替するコミュニケーションツールの延長ではなく、全く新しい第3の空間であると気付かされました。

秋本:これまでのポスター展示による発表の場合は、自分のやったことをまとめて見せる、という自己満足で終わっていたと思います。一方、今回は発表のための空間づくりも手がけたことで、その空間に入って展示を見た人がどう思うかまで、生徒たちが気にするようになりました。例えば、空間を迷路のような形につくり、順路に従って見ていくと、その子の思いが伝わるような形になっている。空間づくりだからこそ生まれる工夫や熱意があると思いました。
宮前:発表のための展示物を作るだけでなく、その展示物をよく見せるための空間のデザインもしなければいけなかったので、生徒たちにとっては大変な工程だっただろうと思います。われわれも
展示空間のデザインをやりますが、展示物そのものと展示空間の両方を自分でデザインすることは、まずないですから。ものすごいチャレンジです。

―生徒たちは、ユーザーの体験デザインまで手掛けていたのですね。
小澤:ポスター展示は来場者に見てもらえばよいのですが、メタバースの場合は空間内をどう移動しながら見ればよいか案内をしないと伝わらない。実際のところ、発表会の当日はかなりの試行錯誤をしました。
1日目のはじめ、来場者にVRゴーグルを渡してそのままにしていると、「これはどうしたらいいの?」と戸惑われてしまう。そこで生徒と相談して、ゴーグルをつけた来場者の横に立って説明をしながら見てもらうよう案内方法を変えました。さらにそれでも説明が不足すると気づき、後日開催した学内のイベントでは、メタバース空間に別部屋からアバターで説明員が入り案内をするという方法をとりました。
武田:人と会話をすることが苦手な思春期の子も、そこで強制的に会話せざるを得ない環境にいられることで頑張るのです。そうした努力が伝わり、結果としてお客さんが満足して、にこにこして帰っていく。この成功体験がもたらすものは、とても大きいと思います。

説明員を担当する生徒が展示の説明や操作のサポートを行った。
―リアルとメタバース空間では、コミュニケーションのあり方にも違いが見えてきそうです。
中村:まさに、今回のプロジェクトで知りたかったポイントがそこです。メタバース空間は心理的安全性にどう影響するのか。もう1人の自分、アバターとなることでコミュニケーション活動に違いが出るかどうかに関心がありました。
リアルの自分とメタバース空間の自分はたぶん少し違っていて、それを楽しむのもまた違う面白さがあると思っています。例えば、英語の授業で、日本人の生徒同士で英語を話すことに不自然さや違和感を覚えることがあっても、アバターどうしであればスムーズに話せるという可能性がある。異文化理解にどう寄与できるのかというのは面白いテーマだと思っています。もしかしたら、今後いろいろな国の人たちが集まり、自分たちのアイデンティティー、文化、習慣について自由に共有するオープンコミュニティが出てくるかもしれない。
コミュニケーション活動自体が、生徒たちにとって自己理解や他者理解の教育的価値をもたらすのです。メタバース空間でのコミュニケーションが新しい学びの価値に繋がると期待しています。
秋本:私は数学科の教員ですので、最初にメタバース空間の活用のお話を頂いた時に、例えば、空間図形がメタバース空間で表現できるから、それを使って教育に生かしたらというアイデアもありましたが、結局、放棄しました。その理由は、数学として育てたい力と、メタバース空間を生かして育てられる力は違うと途中から感じたためです。
無理をして各教科の授業でメタバース技術を利用するのではなく、メタバースだからこそ、普段数学や英語で育てられない、評価できない部分が育ち、評価できる、伸ばせるところに可能性を感じています。学校の活動はいろいろありますが、どうしても言語表現に偏っています。非言語的な表現を育てることにメタバース空間は向いていると思っています。
次なるチャレンジは、メタバースを通じた学びを、より多くの生徒にひらかれたものにすること。各教科でのテクノロジー活用は、学習目的との十分なすり合わせが必要。
―池田さんは、文部科学省による教育現場へのテクノロジー活用に向けた事業を取りまとめるお立場として、様々な取り組みをご覧になられたと思います。いままでのお話からどのような点にご関心を寄せられていますか。
池田:部活動以外への展開拡大に向けた可能性についてぜひ伺いたいと思います。今回は、限られた生徒たちが対象になっていたわけですが、彼らがVRゴーグルを触っているのをほかの子たちが「いいなあ」とのぞきに来るようなことはなかったのですか。「僕も触りたいけれども、駄目なのかな」と・・・。
秋本:ありました。ゴーグルを触る機会自体は提供できたので、触りたい子には触ってもらいました。文化祭のほかに、学内の発表会で体験できるような機会も作りました。
ただ、今回のプロジェクトでは、希望する生徒に、最初に研究計画書を書いてもらい、その内容がよかった子たちに特別の権利として参加してもらったのです。
池田:選抜型のような感じですね。
秋本:実は、私はそこに課題を感じています。ポスターではない、言語化しない方法で表現できることがメタバースの面白さなのに、研究計画書での選考というかたちで、言語化できたかどうかで選抜してしまったためです。美術や音楽ですごく表現ができる子たちのなかには、自分の思っていることと考えていることを言語表現で伝えるのが不得意な子もいます。むしろ、そういう子たちにこそ、メタバース空間をデザインすることから得られる学びの可能性を感じたので、次は計画書などは書かせずにやらせてみたら面白いかなと思っています。

宮前:私は事前審査の必要性については、どちらのパターンもあり得ると思います。まずは、やりたいという強いモチベーションがあって、それを周りに伝えて認めてもらえるようなスキルも重要です。そこからようやく必要な技術を体得していける道が開かれます。社会に出ていくとそういうプロセスが待っていますよね。
武田:今回ははじめての取り組みでしたので、私たちも何人の生徒の面倒を見られるか分からない状態でしたし、機材に限りがあったことなども事前審査をした理由です。実際やってみたら、パソコンがあれば空間はつくれてしまうことが分かりました。あとは指導する私たちが何人の面倒を見られるか次第で間口が広げられます。
今回のプロジェクトに参加した生徒たちが先生になって教えることができれば参加生徒数はどんどん増やせるので、もう少し裾野が広がると思っています。
学年全部の行事にしてしまうことも無理ではないでしょう。全員を分母にしたとき、ひとりひとりからどういう答えが出てくるかは未知数になります。同じ内容でも、いろいろな子がいる中でやると、また違う答えが見えてくると思います。

―全員を対象とするとは、メタバースを利用した学びを授業に組み込むということでしょうか。
武田:そうです。例えば、情報の授業やゼミ活動(探究学習)などが考えられます。カリキュラムは決められているので、メタバースを持ち込むハードルはありますし、教務担当らと相談、交渉が必要になりますが。
中村:ふたつ考えなければいけません。1つは機材の確保等の実現可能性で、もう1つは「なぜやるか」という必要性です。今回、模索しているのは、文章以外で表現することには教育的価値があるのだ、という可能性です。
英語の授業でメタバースによる表現活動が必要かどうかは、私や生徒がそれを必要だと思えば絶対に使いますし、ほかの教科でもたぶん同じだと思います。まずは、やってみて、その次の段階としてはそれが本当に必要かどうか、それが生徒たちのどんな学びになるかを考える必要があります。どんどん検証をして、私たちが振り返りをしてアプローチしなければと思います。
―最後に、本プロジェクト成果の発展・横展開、そして今後の抱負について、どのようにお考えでしょうか。
小澤:例えば、開発したメタバース空間は、ほかの学校の生徒さんと共有することが可能です。技術的にはURLを共有すれば開発したメタバース空間は誰でも使えるものです。もちろん、別の学校で、新たに教室をつくることもできます。
今回の取り組みによるイトーキの成果のひとつは、バーチャルの教室をつくるための要件が抽出できたことにあります。それを横展開させて、生徒数にあわせた教室をつくるなど、今後は要件定義をしながら開発していくことができます。広がりはまだまだあると思います。
もう一つ、メタバース上での生徒の活動は今まで教室内で見えていた活動よりももっと広がりのある活動になります。それをどう「指導する」「フォローする」のかを考えるためにも、デジタルでの活動をきちんと見える化し、評価をするといった生徒支援をするための基礎的な技術も導入も、今後は必要だと思っています。
中村:今回のプロジェクトで試したことをもっと長期的に、かつ、生徒数も増やして実施していきたいと考えています。少ない生徒に対して密にやることはすごく大事ですけれども、メタバース技術を活用した学びがヒットする生徒がほかにどれくらいいるかもまだ分っていませんので、ぜひとも探りたいところです。
もう一つは、もっとメタバース空間にアクセスしやすくして、生徒自身に真剣に遊んでほしいのです。
真剣に遊ぶ、プレイ型の学習のなかで、彼らに学んでいるものを勝手に見つけてほしいのです。私たちはあくまで環境の整備までで、あとは生徒が工夫をして学びに繋げてほしいのです。そちらのほうがたぶん今後のことを考えても楽しいし、長期的に活用してもらえると思います。早くその段階までもっていきたいので、次はそこを目指したいと考えています。

秋本:まさに中村先生が言われたように、生徒たちにとって空間をいじるというハードルが下がり、最終的には私たちが空間を用意しなくても自走できるようになることが理想です。そのためには幾つかゴール設定が必要だと思っています。今回の文化祭はゴールの設定としてよかったと思うので、また来年も続けていきたいと考えています。
ほかにもメタバース空間で表現したいと思えるような目標を設定して、それをやらせてみたいのが一つです。今まで言語能力的には評価されてなかったかもしれない子にこそ、メタバース空間での表現が向いているかもしれないところに、今はものすごく可能性を感じています。
さらに間口を広げて、メタバース空間で表現することがもたらすベネフィットを教員側も知りたいし、生徒とも共有していき、面白さや良さを学校の中で共有し、最終的にそれを発信できればいいと思っています。
まとめ:デジタル・テクノロジーがもたらす多層的な学び
今回のプロジェクトレビューから見えてきたことは大きく2つある。ひとつは、デジタル・テクノロジーの活用がもたらす学びは多層的なものであるということだ。まず、新たなテクノロジーを使いこなす手法を習得するHOWのレイヤーがある。次に、習得した手法を用いて、自分は他者や社会に対してどのように向き合い、またどのように影響を及ぼしていこうとするかを考え、実践するWHATやWHYを探求するレイヤーがある。
そして、もうひとつは、大人たちがロールモデルとなり、指導者としてだけでなく、協働者として生徒たちと向きあうことの重要性ではないだろうか。先生方が「遊び」として新たなデジタル・テクノロジーへの活用を楽しむ姿勢を見せていたこと、そしてイトーキの社員、つまり教員とは違う大人たちが学びに関わり、子どもたちに社会との接点を拓いたこと。これらの要素が、生徒たちにプロジェクトへの前向きな姿勢や主体性をもたらし、他者との交流につながり、自身が及ぼしうる社会への効力感と責任感を芽生えさせたといえるだろう。こうした成功体験こそが、創造性やイノベーティブ・マインドの育成というまた新たな学びのレイヤーを生み出していくのだ。

休み時間にドローン飛行の実験を行う生徒もいるという。
令和4年度 文部科学省 事業成果報告会
https://www.youtube.com/watch?v=7Kr6X7SJc80#t=40m32s
成果報告会資料
https://www.mext.go.jp/content/20230315-mxt_shoto01-100013299_003.pdf
令和4年度 次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416148.htm








